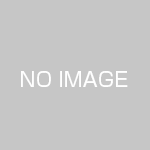こんにちわ、サーフコーチの林です。
館山のRPCから、、、
スプレーの量を増やすには、
トラックを太くしなければ出来ませんよね。
けれど、どうやってトラック太くするのか?
脚力を増やす???
踏ん張る?
ターン時にテールを蹴り込む??
どれも違います。
太ももの大腿四頭筋で踏ん張っても
1カ所の筋肉しか使わないので、
トラックは太くなりません。
蹴り込んだらターンが終わります。
ターンの入りであるコンプレッションの動作で
カラダのパーツ全てを無駄なく乗せて、
インナーマッスルの筋連鎖を使い筋出力を向上させます。
その結果、トラックが太くなります。
コンプレッションをかけるためには
ボードのセンターに自分のセンター(主軸)を合わせ
上半身の軸、両足の側軸を作り、体幹のインナーマッスルを優位にして、
筋肉を連動させてあげるのがスピードを出す基本フォームです。
この基本フォームから体幹の筋連鎖を使いコンプレッションをかけて行き、
立甲を使い脇を効かせる事で深いドライブが掛かったボトムターンが実現します。
立甲することで腕の重さや頭の重さまで、
全てを無駄なくボードに乗せることが出来ます。
ケリー、ジョンジョン、ミックやデスーザやメディーナなどの
ワールドチャンピオンは、常に肩甲骨が寄ること無く
立甲した状態、甲腕一致のゼロポジションで前鋸筋を優位に使いターンをしています。
・背骨部は脊柱筋郡・多裂筋・大腰筋
・腕の動きは、前鋸筋・腹斜筋・腹横筋・横隔膜・大腰筋
と内側と外側の両方のインナーマッスルを連動させ、
筋連鎖を使い更に腕と頭まで全てをボードに乗せています。
しかし、トラックの線が細い、スプレーが少ない・薄いサーファーは
カラダの全てパーツをボードに乗せることが出来ていません。
さらに肩甲骨が寄っているので腕の動きが独立してしまい、
横隔膜から上の肋骨から上が浮いて状態となり、
腕と身体の動きが連動していなくなっています。
手を動かしてもスカスカしたターンになってしまいます。
脇を効かせてボトムターンに入る
カラダの全てを使うためには、立甲させることが重要です。
ボトムターンに入る前に脇を締めるようにしてボトムターンをしてみてください。
ジョンジョンは腕がダラーンと垂れている状態ですが
コンプレッションを掛けるときには、必ず脇を効かせてドライブをかけています。

僕の体感だと、ドライブが掛かりすぎて狙ってたセクション抜けてしまう位スピードが変わります。
脇を効かせてインナーマッスルの前鋸筋を優位に使うとあなたのサーフィンが変わってゆきますよ^^
是非試してみてくださいね。
PS.ターン上手いくなりたい?
体感を優位にして筋連鎖を使うワークや動作を身につける事が出来ます
→サーフコーチングアドヴァンス編残り2名様です